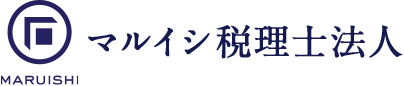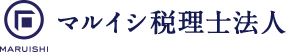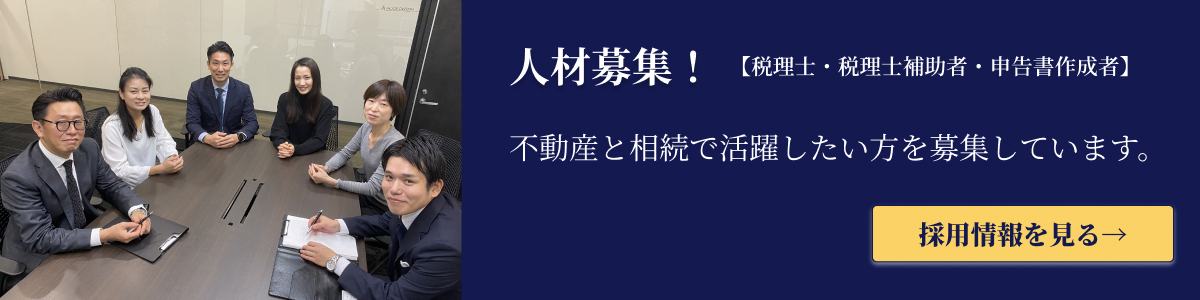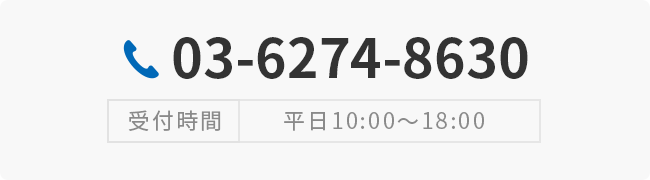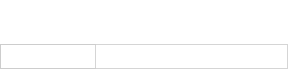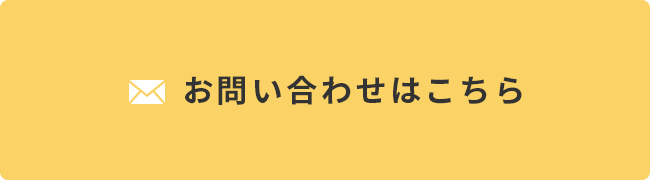相続税の配偶者控除で1億6千万円まで相続税がかからない?デメリットや二次相続を考えた計算事例を紹介
不幸にも配偶者を残して先立つことになってしまう人にとって、一番気になるのは残された配偶者の今後の人生についてでしょう。
「配偶者には無事に財産を相続させることができるのだろうか?」
「税金はどれくらいかかるのか?何か控除できるような制度はないのか?」
など、知っておきたいことや気になることも多いはずです。
ここでは、配偶者の相続税と配偶者控除について詳しく解説していきます。
相続税の配偶者控除とは?
妻が財産を相続する場合、他の相続人とは違い相続税を安くするための特別な優遇措置が設けられています。これを、相続税の配偶者控除といいます。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、配偶者の相続分に関しては法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか多い方の金額までは相続税がかからない制度のことをいいます。
正しくは「配偶者の税額軽減」と言いますが、ここでは配偶者控除で統一しておきます。
配偶者の法定相続分
相続が起こると、遺言書がある場合を除き、民法に定められている法定相続人が財産を相続します。
法定相続人の優先順位(これを「相続順位」といいます)としては、民法では以下のように定められています。
第一順位の相続人の相続権が最優先されますが、第一順位の相続人がいない場合は第二順位の相続人が相続し、第二順位の相続人もいない場合は第三順位の相続人へと順次繰り下がっていきます。
- 第一順位・・・子供(直系卑属)
- 第二順位・・・親(直系尊属)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
妻の場合は、他の相続人の誰よりも優先して問答無用で相続人になることができるため順位には含まれいませんが、配偶者が亡くなっていない限り必ず相続人となります。
配偶者も含めた相続順位は以下のようになります。
- 第一順位・・・配偶者+子供
- 第二順位・・・配偶者+親
- 第三順位・・・配偶者+兄弟姉妹
ちなみに、配偶者の相続権は戸籍上の婚姻関係がある場合にのみ認められています。
したがって、内縁関係にある人物やかつて婚姻関係にあった配偶者などには相続権は認められていません。
ただし、実子に関しては配偶者との婚姻関係がどうであろうと相続権が認められています。
法定相続分の割合
次に、配偶者がどれくらいの相続財産を取得できるのかを見てみましょう。
| 法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子供 | 相続財産の1/2 |
| 配偶者+被相続人の親 | 相続財産の2/3 |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 相続財産の3/4 |
| 配偶者のみ | 相続財産のすべて |
配偶者控除を利用するメリット
この配偶者控除を用いると、相続財産の合計が1億6千万円より少ない場合であれば、配偶者控除を使いさえすれば相続税を0円に抑えることができます。
また、配偶者の法定相続分が高額であったとしても、法定相続分の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。
ただし、配偶者控除を受けるためには期限内に申告書を提出しなければなりません。
配偶者控除を利用するデメリット
配偶者控除が使えるのであれば、とりあえず使えるだけ使った方が得に思われるかもしれませんが、実は必ずしもそういうわけではありません。
なぜなら場合によっては、その配偶者が亡くなった後で子供が財産を相続する時(これを「二次相続」といいます)にかえって相続税が高くなってしまうことがあるからです。
配偶者控除の適用要件
妻の相続で配偶者控除を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
- 相続税を申告する
- 戸籍上の配偶者である必要がある
- 申告期間までに遺産分割を終わらせる
配偶者控除を受けるための条件① 相続税を申告する
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と決まっているため、期限内に間に合うように必ず申告しなければなりません。
なお、配偶者控除を使う場合は相続税額が0円になったとしても相続税の申告を行わなければなりませんのでご注意下さい。
配偶者控除を使う際に必要な提出書類
また、配偶者控除を使った場合は申告書提出時に以下の書類も添付して提出します。
- 被相続人のすべて相続人を明らかにする戸籍謄本
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
- 遺産分割協議書の写し及び相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)
配偶者控除を受けるための条件② 戸籍上の配偶者である必要がある
配偶者控除を受けるためには、相続開始時に被相続人の戸籍上の配偶者でなければなりません。
内縁の妻や元妻などの場合は、残念ながら配偶者控除を受けることができません。
配偶者控除を受けるための条件③ 申告期限までに遺産分割を終わらせる
遺産分割を巡って争いが起こった場合、相続税の申告期限内では話し合いが決着しないことがあります。
このように相続財産が未分割の場合は、とりあえず法定相続分で相続したものと仮定して相続税の申告を期限内に済ませて仮の納税を行います。
ただし、このように期限内では遺産分割が終わらなかった場合は、原則として配偶者控除を使うことはできませんのでご注意ください。(※)
※「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して一度申告・納税し、遺産分割の完了後、分割が行われた日の翌日から4か月以内に申告書を訂正する旨の「更正の請求」を行えば、配偶者控除を適用することができます。
配偶者控除を適用する際に注意したい二次相続
一次相続で配偶者控除を目一杯使って相続税額を0円に抑えてしまうと、二次相続の相続財産が増えてしまう関係で相続税率が高くなり、トータルで見るとかえって増税となってしまう場合があります。
それがなぜ起こるのかについて解説していきます。
相続税の速算表を活用した税率計算
相続税の税率は、所得税などと同じように累進課税となっています。従って、相続財産が増えれば増えるほど相続税率も高くなります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ご覧のように相続税の税率は、財産の取得金額が増えれば増えるほど税率が高くなっていきます。
たとえば取得金額が500万円の場合と取得金額が600万円の場合では、どちらも税率は10%ですからその税額の差は(600万円-500万円)×10%=10万円となります。
しかし、取得金額がすでに6億円の場合と6億100万円の場合では、どちらも税率は55%のためその税額の差は(6億100万円-6億円)×55%=55万円となるため、税金が増えてしまいます。
つまり、同じ100万円であっても、取得金額がどの税率に属しているかで税額が変わってしまうわけです。
一次相続で配偶者控除を使いすぎてしまうと配偶者名義の財産がその分増え、それが最終的には二次相続の財産増加につながるため、結果的にトータルで見るとかえって損をしてしまう場合があるのです。
配偶者控除を活用した相続税計算事例
簡単な例を用いて計算してみましょう。基礎控除や各種特例などはとりあえず考慮せず、条件を以下の内容に設定します。
- 父名義の財産は1億円、母名義の財産は1億円
- 一次相続で父が先に亡くなり、二次相続で母が亡くなる
- 子供は1名
一次相続で配偶者控除をフル活用した場合
一次相続で父の残した遺産1億円をすべて配偶者である母に相続させると、配偶者は1億6千万円までは相続税がかかりませんから、一次相続の相続税は0円です。
二次相続では、父の残した財産の1億円と母の残した財産1億円の合計2億円を子供が相続することになるため、相続税は2億円×40%-1,700万円=6,300万円となります。
したがって、一次相続と二次相続の合計税額は0円+6,300万円=6,300万円となります。
一次相続では法定相続分で財産を相続した場合
一次相続で母と子が5,000万円ずつ財産を相続した場合、母は配偶者控除を使うため相続税は0円となります。
いっぽう、子供の相続税は5,000万円×20%-200万円=800万円となります。
二次相続では、母が相続した父の財産5千万円と母の残した財産1億円の合計1億5千万円を子供が相続することになるため、相続税は1億5千万円×40%-1,700万円=4,300万円となります。
その結果、一次相続と二次相続の合計税額は、800万円+4,300万円=5,100万円となります。
結果として、6,300万円-5,100万円=1,200万円 の差が生まれることになり、一次相続で配偶者控除を使い過ぎるとかえって損をすることがあります。
つまり、配偶者控除を利用する場合は、二次相続まで考えて適用する額を決めることが大切となるわけです。
まとめ
配偶者である妻が相続する場合、配偶者控除を活用することで納税額をかなりの金額まで抑えることができます。
しかし、一次相続での安易な配偶者控除の活用は、諸刃の剣となって二次相続で増税となってしまう可能性があります。
したがって、配偶者控除を利用する際には必ず二次相続までのことを考え、どれくらい利用するのがベストバランスなのかを常に意識するようにしましょう。
相続税の相談は専門家集団マルイシへ
配偶者は他の相続人と比べると相続割合が高く、また配偶者控除を使うことができるため、税制面でも優遇されています。
そのため、配偶者控除を使った一次相続の節税は多くの相続で頻繁に用いられていますが、二次相続まで考えると節税のつもりが増税になってしまう場合があります。
したがって、配偶者控除を使う前には二次相続までを踏まえた相続税のシミュレーションが不可欠です。
妻が相続した財産を最大限残すためにも、事前にあらゆる角度から納税計画を立てておかなければなりません。
とりわけ相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめしております。
マルイシ税理士法人は相続税を専門に取り扱っている税理士がおり、不動産を絡めた相続などにも強いため、さまざまな角度から数多くのシミュレーションや提案をすることができます。
相続税について知りたいことや心配なことがある方は、ぜひお気軽にマルイシ税理士法人の無料相談をご利用ください。