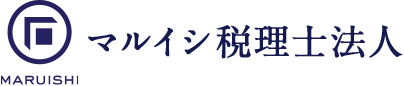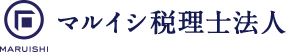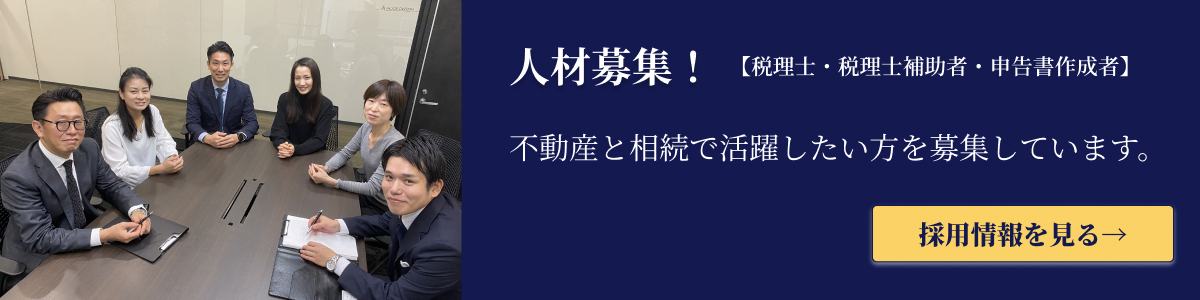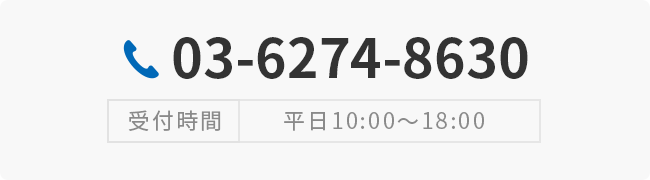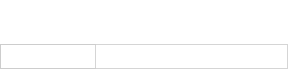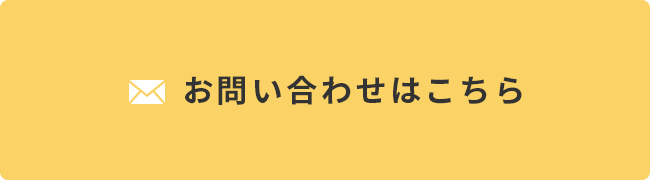銀行預金口座は遺産相続できる?手続き方法や期限・注意点を解説
土地や建物とならび、相続財産のなかで最もポピュラーなものの一つが銀行預金口座です。
ほぼすべての人が銀行口座を一つは持っているため、亡くなった方の相続財産には必ずといっていいほど銀行預金が含まれています。
亡くなった方の銀行預金はどのように相続すれば良いのでしょうか?
また、亡くなってもお金が引き出せるからといって勝手に引き出してしまったら、何か問題が起きないのでしょうか?
銀行預金を相続した場合の正しい手続きの方法や流れ、そして正しく手続きしなかった場合のリスクなどについて解説していきます。
銀行預金口座は相続できる?
亡くなった方の銀行預金は相続財産となるため、相続人同士で誰が預金を相続するのかを話し合い(遺産分割協議)が決着するまでは銀行預金を相続することはできません。
また、相続が起こると、亡くなった方の銀行口座は金融機関にその旨を申し出た時点ですべて凍結されてしまいます。
いったん凍結されてしまうと、引き出すのはもちろん、預け入れも、電気代やガス代などの引き落としもできなくなってしまいます。
手続きを行えば口座の凍結は解除できますし、もちろん銀行の預金も相続できます。
亡くなった人の銀行預金口座は一旦凍結される理由
金融機関が口座を凍結する理由は、相続財産をめぐるトラブルを避けるためです。
もし口座が凍結されなければ、相続人の誰かが勝手に預金を引き出してしまうかもしれません。
そして万が一それを個人的に使ってしまったら、相続財産を公平に分けることが出来なくなってしまいます。
このようなトラブルを未然に防ぐために、口座名義人が亡くなると金融機関は口座を一旦凍結するようにしているのです。
ちなみに、相続人が金融機関に亡くなった旨の連絡をしなければ口座の凍結を防ぐことができますが、金融機関は独自の方法で口座名義人の死亡事実をチェックしているため、多くの場合亡くなってから数日以内には銀行口座が凍結されることになります。
凍結された銀行預金口座は解除できる
一旦凍結された口座を解除し、銀行預金を相続するためには、名義変更の手続きを口座のある金融機関ごとに行うことで可能です。
取引金融機関が一行だけであれば楽なのですが、複数行に渡る場合は同じ手続きを何度も行わなければならず、その都度書類を作成しなければなりません。
※遺産分割協議で預金の相続が決まった人以外は、名義変更の手続きは行えませんし行う必要はありません。
銀行預金口座の名義変更の期限
名義変更のための手続き自体には期限がありませんが、相続税の申告は相続開始の日から10ヶ月以内に行なわなければなりません。
納税資金の準備などもあるため、名義変更の手続きは出来るだけ早く済ませておいた方が良いでしょう。
しかし、名義変更を行わなければ預金は凍結されたままになり、10年が経過すると休眠預金となってしまいます。
もちろん、休眠預金になっても預金自体が消滅したり没収されたりするわけではありませんが、口座の管理は金融機関から預金保険機構に移されることになります。
銀行預金口座の相続に必要な手続きとは?
銀行預金を相続するためには名義変更の手続きが必要となります。
手続きを行うためにはどのような書類が必要で、どのような流れで手続きが行われていくのかを見てみましょう。
銀行預金口座の名義変更と手続きの流れ
銀行預金を相続する場合の手続きは、おもに以下の3つに分けることができます。
- 金融機関に申し出る
- 必要書類を提出する
- 払い戻し手続きを行う
①金融機関に申し出る
相続が発生したらまず、亡くなった方の銀行預金がある金融機関の各支店に亡くなった旨の連絡を行います。
この時、実際に相続するために必要な書類などの説明や案内が金融機関から行われます。
もしこの手続きを行わず放置しておくと、相続人(もしくは相続人以外)の誰かが勝手に預金を引き出してしまうかもしれません。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、相続が発生しだい出来るだけ早い段階で、金融機関に連絡を行っておかなければなりません。
②必要書類を提出する
次に、相続手続きに必要な書類を集めて金融機関に提出します。
なお、手続きに必要な書類は、相続の状況や各金融機関によってことなります。
そのため、金融機関の説明に従い、それぞれに必要な書類を集めていきます。
③払い戻し手続きを行う
銀行預金の相続手続書類を各金融機関に提出すると、払い戻し等の手続きが行われます。
一般的には、必要書類を提出してから10日前後で預金の払い戻し手続きが完了します。
銀行預金口座の相続に必要な書類について
銀行預金を相続するために必要な書類は、遺言書がある場合とない場合によってことなります。
また、遺言書も遺産分割協議書もない場合や、家庭裁判所による調停などがある場合によってもことなりますが、
銀行預金の相続に必要な書類は、相続の状況によっておもに以下の4つに分類することが出来ます。
- 遺言書がある場合
- 遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
- 遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
①遺言書がある場合
遺言書がある場合、銀行預金の相続を行うためには遺言書および遺言書が検認されたことを証明するための書類が必要となります。
なお、遺言書の内容により必要な書類はことなりますが、おおむね以下の書類が必要となります。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 亡くなった方の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
- 預金の相続人の印鑑証明
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
②遺言書はないが遺産分割協議書はある場合
遺言書はないが遺産分割協議書がある場合、銀行預金の相続を行うためにはおおむね以下の書類が必要となります。
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名と実印による捺印があるもの)
- 亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(生まれてから亡くなるまでの間のすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
③遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合、銀行預金の相続を行うためにはおおむね以下の書類が必要となります。
- 亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(生まれてから亡くなるまでの間のすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
④家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合、銀行預金の相続を行うためにはおおむね以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本もしくは審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、これらに加え審判確定証明書も必要となります)
- 銀行預金を相続する人の印鑑証明書
このように、銀行預金を相続するために必要な書類は相続の状況によりことなります。
そのため、各金融機関の説明にしたがい、相続の状況に合わせて必要な書類を集めていかなければなりません。
すぐに現金が必要な場合に活用できる払戻制度
相続人同士による調停や審判の申し立てが行われている場合は、家庭裁判所へ申し立てを行うと、預金の全額または一部を(仮に)取得することができます。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
亡くなった人の銀行口座は死後に一旦凍結されてしまいますが、葬儀費用の支払い等で問題が起こってしまう場合があります。
このような事態を避けるため、2019年の7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。
この制度を活用すると、亡くなった人の葬儀費用などを故人の銀行口座から150万円以内という上限付きで引き出すことができるようになります。
引き出し金額の上限は、以下の式により算出された金額となります。
たとえば、相続開始時の銀行預金の残高が600万円、相続人が配偶者と子供1人の合計2名の場合、
配偶者が単独で「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用して引き出すことのできる上限金額は、次のようになります。
※必ずしも上限いっぱいの150万円を引き出せるわけでないという点には注意しておかなければなりません。
金融機関で直接手続きを行う場合に必要な提出書類
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用するためには、以下の書類を金融機関に提出しなければなりません。
- 亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
銀行預金を相続する場合に注意すべき点について
では最後に、銀行預金を相続する場合に注意すべき点についてまとめてみます。
注意すべき点① 相続税が課税される場合がある
相続税には基礎控除といわれる非課税枠があります。そのため、基礎控除を超える金額の銀行預金を相続すると、相続税が課税されることになります。
なお、相続税の基礎控除は以下の式で算出することができます。
たとえば、相続する銀行預金の金額が合計で5,000万円、法定相続人が子供2名の場合、相続税の基礎控除は次のようになります。
この結果、相続する銀行預金の金額(5,000万円)が基礎控除(4,200万円)を超えてしまっているため、差額に対して相続税が課税されます。
もちろん、銀行預金以外にも相続財産があればそれらも相続税の対象です。
このように、銀行預金を相続する場合、金額によっては相続税が課税される場合があるため注意しなければなりません。
注意すべき点② 相続する前に引き出さない
上述のように、亡くなった方の銀行口座は金融機関がその事実を知った日から一旦凍結されます。しかし、凍結前であれば引き出すことができます。
ただし、亡くなった人の銀行口座から相続前に預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したものとみなされるため、相続放棄ができなくなってしまいます。
通常であれば亡くなった人に財産よりも多い額の負債があった場合、相続の事実を知った日から4ヶ月以内に手続きを行うと相続放棄することができます。
しかし、亡くなった後で銀行口座から預金を引き出してしまうと、たとえそれが少額であっても相続放棄ができなくなってしまいます。
このようなリスクを未然に防ぐためには、相続をする前に銀行口座から預金を引き出さないように注意しなければなりません。
まとめ
亡くなった方の預金口座は金融機関によって一旦凍結されますが、これは決してペナルティーではなく、さまざまなリスクを未然に防ぐための配慮から行われるものです。
口座が凍結される直前にある程度引き出しておく話はよく聞きますが、後の争いを誘発する恐れがあり、また相続放棄ができなくなるリスクも生じてしまうため、控えておいた方が賢明でしょう。
亡くなった方の銀行預金は相続することができますが、そのためには遺言書の相続人となるか、遺産分割協議により預金を相続しなければなりません。
また、相続した預金は相続税の納税に使われることが多いだけに、相続する額については相続人それぞれの納税額に配慮した方が良いでしょう。
ただし、相続税にはさまざまな節税方法があるため、実際にどれくらいの相続税が必要となるかは税理士などの専門家に相談することをお勧めします。