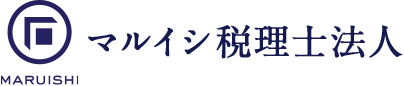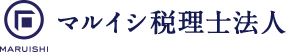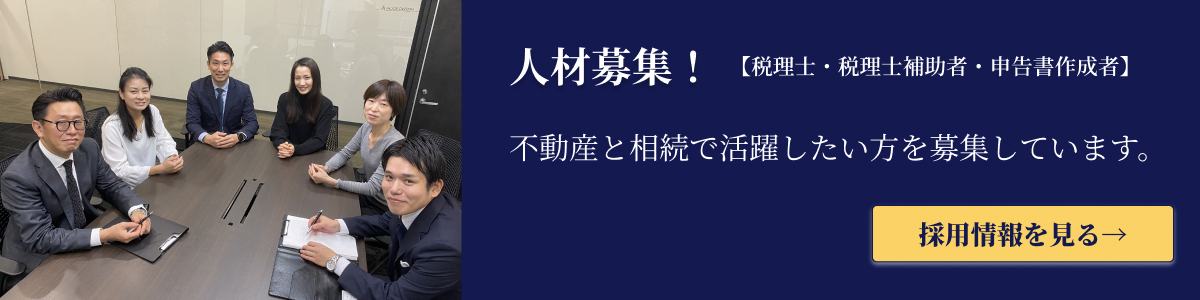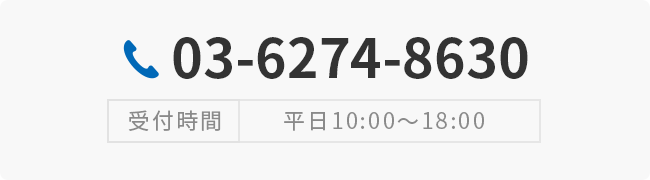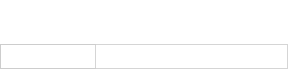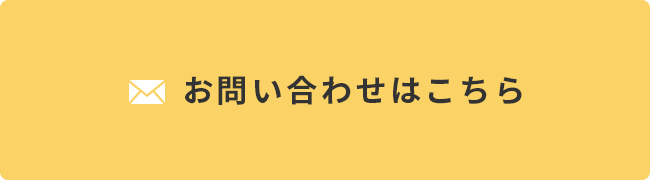いとこの遺産は相続できない?特別縁故者の申し立てと生前での相続対策
いとこに配偶者や子など法定相続人が誰もいないような状況のとき、故人のいとこは遺産相続をできないのが基本です。
しかし、特別縁故者の申し立てや生前のときの相続対策によって相続が可能になるケースもあります。これらの具体的な方法について解説します。
いとこの財産は遺産相続できない
基本的な考え方からいえば、故人のいとこは遺産相続をできません。まず、その理由を確認しましょう。
いとこの財産を相続できない理由
いとこは法定相続人ではない
民法において、いとこは法定相続人にはありません。したがって、故人のいとこは財産を相続できません。
下記をご覧いただくとわかるように、いとこは法定相続人の範囲に入っていません。
| 優先順位 | 血族の内容 |
|---|---|
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 子および代襲相続人 |
| 第2順位 | 両親などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
法定相続人と遺産相続の優先順位についてさらに詳しく知りたい方は下記記事も読んでみてください。
関連記事:遺産相続の相続順位とは?法定相続分と法定相続人が持つ権利について解説
身寄りのないいとこの遺産でも相続できない
いとこに配偶者・子・両親など、法定相続人が誰もいないケースでも結論は同じです。いとこは遺産を相続できません。受け継ぎ先のない「相続財産」は国のものになります。
故人のいとこの財産を相続する特別縁故者の申し立て
いとこは法定相続人ではないため、基本的には相続することは難しいですが、「特別縁故者の申し立て」によって相続できることがあります。
特別縁故者とは?
故人と親密だった人や故人の生活を支えた人のことです。法律上の特別縁故者は次のような人のことです。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の療養看護に務めていた人
- 1または2に準じて特別縁故のあった人
1の代表例は「内縁関係にあった」あるいは「事実上の養親子だった」などのケースです。
本稿のテーマでいえば「いとこと内縁関係だった」「いとこと長年、家族のように生活を共にしていた」というケースが考えられます。また、2は一時的な世話というより、「長年献身的に療養看護をしていた場合」などがあてはまります。
特別縁故者になるための手続き
ただし、本人がいくら「故人と親密だった」「生活を支え続けた」と主張しても、家庭裁判所で申し立てを行いそれが認めらなければ特別縁故者として、いとこの財産を受け継ぐことはできません。
この手続きは、「(特別縁故者による)財産分与の申し立て」といわれますが、申し立てからそれが認められ財産が分配されるまでの流れは次の通りです。
- 相続人と親密だった人などからの申し立て
- 家庭裁判所による「相続財産管理人」の選任
- 相続財産管理人による相続財産の整理(債務の支払いなど)
- 官報に相続人の捜索を公告
- 一定の期間内に相続人の権利の主張がなかった場合、相続人不在確定
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て
- 特別縁故者への財産分配
大きな流れは、まず「相続人がいないことを確定」させて、その後に「特別縁故者に財産を分配」するというものです。なお、申し立てから財産分配までは、少なくとも10ヵ月以上かかります。
特別縁故者として相続した場合の注意点
相続分の割合は裁判所によって決定される
家庭裁判所によって特別縁故者への財産分配が認められても、故人の財産をすべて引き継げるとは限りません。たとえば、法定相続人が1人の場合はその人が100%の財産を引き継げますが、特別縁故者の場合は家庭裁判所が相続分の割合を決めます。仮に、相続分の割合が50%なら半分の財産しか引き継げません。
特別縁故者が引き継いだ財産の相続税は「2割増」になる
特別縁故者の引き継いだ財産は、相続税の対象になります。流れとしては、まず基礎控除額を差し引き、残りの財産に対して相続税が課せられることになります。基礎控除額の計算式は、「3,000万円+(相続人の数×600万円)」です。特別縁故者の場合、相続人の数が0人のため3,000万円が基礎控除額になります。
注意したいのは、特別縁故者の相続税は「2割増になる」という決まりです。たとえば、通常の相続税が2,000万円なら、特別縁故者は2,400万円を納めるということです。
いとこの財産を相続するために生前から行うべき対策
ここまでの内容で「故人のいとこは財産を相続は難しい」という内容をお伝えしてきましたが、生前から相続対策をしっかり進めていれば、スムーズにいとこの遺産を相続することも可能です。
生前から行う対策としては、下記方法があります。
このうち、どちらかを採用してもよいですし、両方を採用する手もあります。
- いとこに遺言書を作成してもらう
- いとこから生前贈与をしてもらう
いとこに遺言書を作成してもらう
いとこと遺産相続のことを気兼ねなく話し合えるような仲であれば、遺言書を作成してもらい、そこに「財産のすべて(または一部)を遺贈する」旨を記述してもらうのがもっとも確実な相続対策です。
仮に、口約束で「財産を遺贈する」と話していても、証拠がなければ法定相続人ではないため、いくら親密な仲でも財産を遺贈できない可能性があります。
この選択をしたときの注意点は、法的に効力のある体裁・内容の遺言書を作成することです。遺言書が法的に無効であれば財産を遺贈できなくなります。
公的証書遺言がおすすめ
一般的な遺言書作成の選択には「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」があります。ご自身の自筆で記述する「自筆証書遺言」は不備が出やすいため、弁護士や司法書士などの専門家の指導に基づき作成するのが賢明です。
一方、元裁判官や元検察官など法律の専門家の助言に基づいて作成する「公正証書遺言」は、無効になるリスクがほぼありません。「相続できないリスクをなくすこと」を最優先するのであれば、公正証書遺言の選択がよいでしょう。
いとこから生前贈与をしてもらう
こちらの選択も「いとこと相続について話せる仲なら」という条件付きです。生前贈与によって、いとこが生きている間に期間をかけて財産を譲り受けていくことも可能です。
なお、前項でご紹介した「遺言書を作成してもらう」と「生前贈与をしてもらう」を併用することで相続税対策にもなります。なぜなら、生前贈与によって財産が減ればその分、相続税を抑えられるからです。
生前贈与のやり方
生前贈与の具体的なやり方としては、年間110万円以下の範囲内で生前贈与をしていく「暦年贈与」がおすすめです。年間110万円以下の非課税枠の範囲内であれば贈与税がかかりません(贈与税の申告も不要です)。
まとめ
ここでは、「いとこと相続」をテーマについて解説してきました。最後に本稿のポイントを振り返ってみましょう。
まず、故人のいとこは遺産相続できないのが基本的な考え方です。
理由は、いとこは法定相続人でないからです。なお、法定相続人がいない場合も故人のいとこは相続できません。
ただし、「死後の特別縁故者の申し立て」と「生前の相続対策(遺言書作成、暦年贈与)」を行うことによっていとこの財産を相続することができるケースもありました。
死後の特別縁故者の申込みにおいては、財産の額が多いと相続税を納める必要がありますが前述の通り、基礎控除を差し引いたり、通常の2割増しになったりなど独特なルールがあります。
また、生前の相続対策においては、贈与税・相続税をなるべく抑えるスキームが必要です。
こういった事情から、いとこの財産を相続する(または相続したい)場合は、早い段階から税理士にアドバイスするのが安心です。
顧問税理士がいらっしゃらない人は、私が所属しているマルイシ税理士法人の無料相談をお気軽にご利用ください。